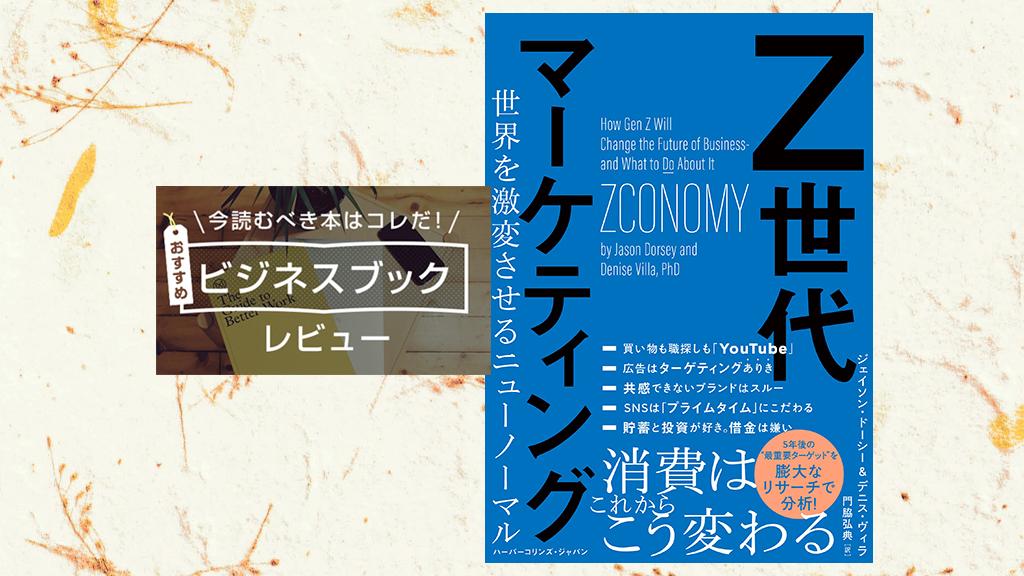麻倉:次に取り上げるのは、平成のソニーが世界に誇る傑作プロジェクター「QUALIA 004」です。
「QUALIA 004」こと「Q004-R1」「QUALIA」は人の心に訴える“モノづくり”を目指して、平成13(2001)年5月に当時の出井伸之社長が発足させたプロジェクトです。語源は脳が質感を感じる力を意味する、感覚質“クオリア”。ソニーコンピュータサイエンス研究所上級研究員の茂木健一郎博士がメディアで発信したことで、世間的な認知度が高まりました。ブランドとしては平成15(2003)年にスタート。ハイクオリティ志向で技術オリエンテッドな高級製品を揃えるため、社内に設けた「クオリア認定委員会」が企画を審査し、認定を受けた製品に3桁のクオリアナンバーが与えられるというものでした。
QUALIAの発表会に登壇した出井伸之CEO(2003年当時)その4番目に企画が通ったプロジェクターは、エポックメイキングという言葉が大袈裟でなく、プロジェクターの偉大なるマイルストーン、映像の歴史に残る技術文化遺産となりました。
QUALIA 004は1,920×1,080のフルHD解像度に対応した初の家庭用SXRDプロジェクターです。業務用DLPプロジェクターは720pパネル搭載機が主流だった当時において、圧倒的な解像感で業界に大きな衝撃を与えました。ですが見どころはそこに留まらず、ディテールまで見事に解像する細密描画力さることながら、色再現性にはとにかく驚嘆しました。
この頃の私は映像の評価要素を「表示/再現/表現」という三段階で見ていました。それで言うとQUALIA 004は像表現におけるボキャブラリーが実に豊富であり「表現力」が深い。コンテンツの映像文法に沿った再現力に加え、このプロジェクターは明らかにコンテンツ側の意図に寄与し、それと共同作業での深い表現をものにしています。そのため情緒系映像の再現性が抜群に良かったのが印象的です。
特に暗部の微妙な色の違いが実に上手く、しかも凄みを持って再現されていました。透過型液晶デバイスに見られた暗部のS/N問題も、反射型液晶(LCOS)のSXRDデバイスでは無縁で、映像に透徹した描写性を与える一因となっています。人肌を見てみれば、肌色に込められた意図的な情報の驚くべき深さに圧倒。映像の背景にある文脈的な情報がここまで的確に捉えられるプロジェクターは史上初ではないでしょうか。美味しく再現される白ピークも、映像の意味を語る重要な小道具になっています。
「QUALIA 004」に搭載されたSXRD具体的な要素を言うと、画調としては若干コントラストが甘く僅かな黒浮きが見られるものの、LCOSデバイスの特長である階調で迫ってきます。しかも絵の品が良い。DLPデバイスは、あまり解像感が無くこってりとした色乗りのものが多かったのに対して、こちらは色が少々細身美人で彩度感がゴージャス、色数が驚くほど多く、しかも色のグラデーションが緻密でした。ここまでのスクリーン映像は覚えがない、そういうレベルです。
ナチュラルで素晴らしい色再現は「太陽光と同じ豊富な色スペクトルを持つ」というキセノンランプの絶大な効果によるもの。特に赤・橙・山吹色の描き分けが正確で、花を映すと微妙に色合いが違う花弁の数々が丁寧に描き分けられていました。当時も他社にキセノンランプ使用を謳う製品が無かったわけではない(それも業務用で、家庭向けではない)ですが、感動性においてこれまで観てきたものとは圧倒的に違います。「この映画って、そんな映像意味があったのか」「撮影監督はここまで凝っていたのか……」そんなコンテンツの深掘り、探求、新発見が得られました。
放熱フィンを備えたキセノンランプその一部が外から見えるデザインになっていた――僕がオーディオビジュアルの世界に足を踏み入れたのはこの頃でした。当時地元の関西で、心斎橋から今のソニーストアがある梅田へ移動したQUALIA大阪へ突撃し、一番奥の視聴ブースでQUALIA 004を視聴させてもらいました。それまで視たことのない豊かな色彩の巨大な映像に、それまでの常識が音を立てて崩れていったことを、今でも鮮明に覚えています。
麻倉:注文付けるとするならば、黒のペデスタルレベルでの沈みがもっと欲しいという点くらいでしょう。色要素がたいへん素晴らしいだけに、そこがややアンバランスです。それにしても3板式からLCOSまで、この時で既に20数年以上にわたってあらゆるフロントプロジェクターを見続けてきた私でさえも「これほど色の情報量が多い固定画素型プロジェクターなど見たことがない」と感じたほど。私が感動するソニー製品は滅多にないが、これは本当に凄いと思いました。
これから2011年に登場した民生用初の4Kプロジェクターである「VPL-VW1000ES」まで、ソニーはプロジェクターにおけるイメージリーダーを張り続けました。以降のプロジェクターはプラスチック筐体が主流になり、存在感が薄れてゆくだけにQUALIA 004のモノとしての作り込みの凄さは圧倒的。デザインと質感・素材感も素晴らしいです。これは掛け値なしに「10年に1度の出来」と評して過言ではありません。
さて、このプロジェクターを語る時には、QUALIAというブランドが犯した失敗に触れないわけにはいきません。
'95年からソニーはIT化に舵を切り、水平分業への転換に動きます。水平分業は技術力を持たない企業でも市場参入にできる代わりに、他社との差別化が難しくなりコスト競争へ収束する。量産効果によるシェア伸長と引き換えに、製品の単価下落に陥るのです。行き着く先は市場に同じようなモノが溢れかえる、経済学用語で言うところの汎用品化・コモディティ化です。

そこでソニーは垂直統合的こだわり技術を打ち出して、デジタル時代でも差別化を図ります。その流れにおいて、行き過ぎたIT志向のアンチテーゼとして打ち出されたのがQUALIAでした。出井さんはIT時代におけるハイエンドAVに、かなり高い志で向き合っていた訳です。
ユニークな発想と最先端のモノ作りの精神をデジタルに生かしたハイエンド商品作りは「技術の揺籃」として絶対必要です。それがブランドの、ひいては企業そのものの価値を高めるのです。しかし同じ様なルーチンワークを繰り返す通常の仕事の延長では“明日の種”は作り難い。究極を目指す開発の中で飛躍的なテクノロジーも生まれ、ハイエンドとしての大胆な差別化につながる。それには時間と人員とお金のリソースが要求されます。
――逆に言うと、単なる高級部材の組み合わせでは、ハイエンドを名乗るに相応しい技術の飛躍はなかなか起きません。頂点へ向かうストイックさが“高級品”と“高価格品”の絶対的な差であり、ブランドの根拠のひとつとなる訳ですね。
麻倉:そうです。そうして出来上がった新技術が次世代のスタンダードとして採用され、普及する。技術であれ芸術であれ、人を感動させるモノは、上から降ろさない限りなかなか出てきません。QUALIAのビジネスは“シャワー効果”でソニー全体の技術水準を上げるという、非常に技術戦略的な面を担っていました。一方で現場から見ると、QUALIA 004はそれまで業績としてなかなか認められなかった高級プロジェクタ開発に、しっかりとした予算が充てられました。
この様な思想は素晴らしい。ただしQUALIAの実態は、製品の出来が玉石混交でした。これはたいへんな問題です。
デジタル時代は技術革新が非常に速く、次々と新製品が登場する。しかもそれは共通“規格”という枠の中で起こります。この様な状況の中で、QUALIAにはハイエンドで、モノの価値観があり、モノを愛でる対象という“企画”が要求されました。少なくとも五年程度は銘品としての魅力を放ち続ける事が必要。すぐに陳腐化するものはQUALIAブランドを冠する意味がないのです。
ところが「QUALIA 005」が与えられた液晶テレビは、三原色LEDバックライトという実験的な挑戦を仕掛けたものの、画質を見るとトータルでは翌年に発売されたBRAVIAの方が良かった。当時において液晶テレビはまだまだ発展途上の製品カテゴリーであり、そこでQUALIAブランドを展開してはいけなかったのです。
「QUALIA 005」。左から46V型の「KDX-46Q005」、40V型の「KDX-40Q005」オーディオ製品はさらに問題でした。SACDシステム「QUALIA 007」は、トレイ部分の動作こそユニークだったものの、オーディオとしての本質である“圧倒的に人を感動させるという音作り”が欠けていました。小型デジカメ「QUALIA 016」は、不具合・製品回収問題を起こし、QUALIAブランドのイメージを大きく傷つけました。
SACDシステム「QUALIA 007」。デジタルアンプ内蔵のSACDプレーヤー「Q007-SCD」と、スピーカーシステム「Q007-SSS」で構成された小型デジカメ「QUALIA 016」こうした実製品の迷走に加え、悪化の一途を辿っていた経営状況がQUALIAブランドに追い打ちをかけます。結局は出井さんの退任をきっかけに、平成18(2006)年にブランドは終息しました。
――平成17(2005)年にCEOの座に就いたハワード・ストリンガー氏は、生き残りのため削ぎ落とす経営を選びましたが、これは当時のソニーに必要だったものだと思います。
麻倉:一方で、超解像技術をベースにしたクリエイションボックス「QUALIA 001」や、SXRDリアプロテレビ「QUALIA 006」、ブラウン管モニター「QUALIA 015」など、映像分野の製品には大傑作と言っていい製品が多いです。前述のLED液晶テレビは別にして、QUALIAの映像製品はデジタル技術を使いつつ、他社が絶対真似できないところをやっていました。
クリエイションボックス「QUALIA 001」SXRDリアプロテレビ「QUALIA 006」ブラウン管モニター「QUALIA 015」QUALIAから生まれたSXRDは、その後フロントプロジェクターやリアプロなど普及製品に落とし込まれました。QUALIA 001の中枢である「DRC」は、鬼才・近藤哲二郎氏が創った高画質化回路であり、ソニーにおける画質の要として改良を重ねながら、現在もなおテレビやレコーダーなどに搭載され続けています。同類のデータベース型アップコンバートは、今やAI高画質化の世界標準的な手段。これも大きな成果でしょう。
その意味で004はQUALIAの理想を最も体現した製品です。ハイエンドからのシャワー効果という意義は、ビジュアル製品においてはとても大きかった。QUALIAの最高傑作であり、ブランド最大の意義でもあると言えます。
――今に続くソニーのプロジェクターは、絵も色もデザインもQUALIA 004が原点になっている事は確かですね。
麻倉:幸いなことにQUALIA的な因子がソニーの内部から消えることはありませんでした。当時で言えばAVアンプ「TA-DA9100ES」が、それに該当するでしょう。ハイエンドスピーカー「SS-AR1」は10年以上も生産され続けており、これは今でも新品を購入できます。
そして2012年に平井一夫さんがCEOに就任して以降、近年では高級ウォークマン「NW-WM1Z」に連なる「Signature Series」なども徐々に出てきだしました。厳しい冬の時代は長かったですが、ソニーは間違いなく復活の道を歩んでいます。